戸山翻訳農場
作業時間
月曜 14:45~18:00
木曜 16:30~18:00
金曜 18:00〜21:30?
ブログ
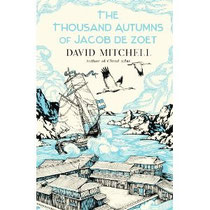
【今回はイギリス編】
「The Thousand Autumns of Jacob De Zoet」の著者デイヴィッド・ミッチェルは1969年イギリス生まれの小説家。現在は日本人の奥さんとともにアイルランドに住んでいるという。1999年にデビューし、本作は第五作目。権威あるイギリスの文芸賞「ブッカー賞」の最終候補にも度々名を連ね、イギリスの人気文芸誌「グランタ」からは2003年に“期待の若手イギリス小説家 20人”の一人としてその名前が挙げられた。日本では、新潮クレスト・ブックスで小説第二作『ナンバー9ドリーム』(高吉一郎訳)のみが出版されている。
彼は2007年にアメリカTime誌の「世界で影響力のある100人」にも選出されており、その人気がイギリス国内だけでなく世界規模のものであることがわかる。さらに小説第四作「Cloud Atlas」(クラウド・アトラス)は、映画『ラン・ローラ・ラン』のトム・ティクヴァと『マトリックス』のウォシャウスキー兄弟(※兄のラリーは性転換し、今は“ラナ”と名乗っている。ウォシャウスキー姉弟とするのが正しいかもしれない)の共同監督によって2012年10月26日にアメリカで公開される。日本でも2013年の公開が予定されている。
「Cloud Atlas」の予告編はなんと約6分もあり、監督たちはその理由を「物語のスケールが大きくて説明するのが難しかったから」と語っているのだが、この言葉はデイヴィッド・ミッチェル作品の特徴をよく表している。複数の視点から複数の時代も場所も異なる物語が描かれ、それらの物語がやがて交差してゆく……物語はスリルあり、サスペンスあり、ロマンスあり、そしてSF的でもある。本人もその影響を公言しているが、作風は近年の村上春樹小説にも似ている。
さて、「The Thousand Autumns of Jacob De Zoet」である。舞台は長崎の出島。江戸の寛政時代、18世紀末から19世紀初頭にかけての物語だ。主人公はオランダからオランダ東インド会社の会計係として日本の出島にやってきたJacob De Zoet(ヤコブ・ダズート)。物語の後半で、日本が “The Land of a Thousand Autumns”(千の秋を持つ土地)や“The Root of the Sun”(日のいずる処)と呼ばれているという言及があり、タイトルの“The Thousand Autumns of Jacob De Zoet”は「ヤコブ・ダズートの日本滞在記」といった意味であることがわかる。
本作には数十以上の人物が登場し、それぞれの物語が語られるが中心となるのはオランダ人医師マリヌスに学ぶ助産婦のアイバガワオリト、通詞(江戸幕府公式の通訳)であるオガワウザエモン、そしてダズートの物語である。五部構成469ページにも及ぶ大著であるが、一部から三部でこの三者が中心の物語が描かれ、実に451ページが費やされている(四部と五部は、ページこそ少ないがそれはそれは驚きと感動に満ちている)。
一部では、オリトとダズートの交流、オリトに好意を寄せるダズート、その気持ちを知るウザエモン、そんな中負債を抱えたオリトは寺に送られる。寺にはある秘密があり、オリトの身に危険が迫る…。オリトの救出に向かうのが第二部。寺の秘密を知ったウザエモン、幕府の陰謀や、ダズートの想い、救出計画を巡り様々な思惑が交錯し、計画は意外な形で幕を閉じる。第三部は、出島にやってきたイギリス船が、オランダから日本との交易権を奪おうとするもののなんとか窮地を脱するダズートが描かれる。
物語の構成、至るところに仕掛けられた伏線、謎が解き明かされていく過程。紹介したいところは山ほどあるのだが、「スケールの大きな歴史小説」的側面と「通詞」の存在こそが本書の大きな特徴だと思われるのでそちらの方を取りあげてみたい。

「The Thousand Autumns of Jacob De Zoet」には杉田玄白や前野良沢など、当時実際に活躍していた人物が登場する。史実に基づいた小説のように見えるが、年代や事件の詳細などは微妙に変更が加えられており、史実からインスパイアされて書かれた小説だと言える。例えば、これはいくつかの書評サイトでも指摘されているが、主人公ダズートは1803年から1817年まで出島のオランダ商館長を勤めたヘンドリック・ドゥーフという実在の人物がモデルになっている(右図参照)。第三部でやってきたイギリス船は「フィーバス号」だが、ドゥーフ在任時の出島には「フェートン号」がやってきて、オランダ商館員を拿捕する「フェートン号事件」が起こっている。
ドゥーフは1803年から17年まで日本にいたそうだが、ダズートは1799年から1817年までいたという設定に変更されている。そしてそのことで、ダズートは世界史の波に翻弄されることになる。「フィーバス号」の来襲は、大きな歴史の流れを象徴している。ダズートがやってきた1799年の末には、オランダ東インド会社が解散。先駆けること6年、1793年にはネーデルラント連邦共和国(オランダ)はフランスの支配を受け崩壊。1795年にバタヴィア共和国というフランスの衛星国家となっていた。このときのフランス軍で活躍し、名を挙げていたのがナポレオン・ボナパルトである。そんななか、フランスと敵対していたイギリス帝国は、東南アジアの植民地を接収した。「フィーバス号」がやってきた背景にはこのような世界史の動きが関係していたのである。こうした動きはもちろん本書の中で描かれるが、他にも、東インド会社内の人間関係、イギリス船の思惑なども相まって、ダズートが巻き込まれる歴史の波は、臨場感を持って読者に体験される。
そしてさらにこの物語を魅力的なものにしているのが通詞たちの存在だ。日本とオランダ、オランダとイギリス、本書には異文化の交流がいたるところで起きるがそこには必ず、彼らがいる。政治的決定の場面で通訳をするために最適な言葉を探そうとする緊迫した場面もあるが、なかにはこんな微笑ましいシーンもある。
「あの、ですね、オウハンドが言うには漢字の“じゅう”は……」バツが悪そうにしながら、ヤコブは紙に文字を書きだした……こんな風に……
千
「だが私はオウハンドに言ったんだ、違う。“じゅう”という文字は…こうだろうと…」
百
ヤコブは書き順を間違えていたがそれは彼の不慣れさを強調していた。「中国の商人は私たち二人とも間違っていると言い張るんだ。彼は―」ヤコブは眉をひそめてため息をついた。「— 十字を書いた。たしか、こんな……」
×
「それで私はこの中国商人は詐欺師だと確信したんだ。言い過ぎかもしれないが。小林通詞、申し訳ないが正解を教えてくれないだろうか?」
「オウハンドさんの数字は」小林は一番上に書かれた数字を指差して言った。「“せん”です。“じゅう”ではありません。ダズートさんの数字も、同じく、間違っています。その数字は“ひゃく”です。そしてこれは」×を指して言う。「記憶違いかと。商人が書いたのはこれでしょう……」小林は筆で書き始めた。「これが“じゅう”です。二画で、そう、一画は縦、もう一画は横……」
十
言葉を学んで行くのは、なにもダズートたち外国人だけではない。日本の通詞や学者たちもまた、彼らの言葉を学び、理解しようと試みる。オランダ語の『ターヘル・アナトミア』が日本語に翻訳されたのは1774年。これが初の西洋語からの翻訳本として知られる『解体新書』である。その訳者杉田玄白が、作中、この翻訳作業について語るシーンがある。
「作業は大変に骨の折れるものでした」杉田玄白は房のような白い眉を整えながら言った。「一つの言葉を探すのに何時間も費やしました。結局、対応する日本語がないということもしょっちゅうでした。だから言葉を創りだしました、この国の人々が ——」古老にうぬぼれた様子はなかった。「永遠に使うだろう言葉を。その一例は、蘭語の“nerve”という言葉に対して考えだした“神経”という言葉です、牡蠣を食べているときに思いつきました。私たちは、ことわざを借りれば『一犬影に吠ゆれば百犬声に吠ゆ』です……」
デイヴィッド・ミッチェルは日本で数年間英語の教師をしていた経験があるからかもしれないが、英米圏で活躍する作家のなかにも、言葉の伝わらなさや翻訳に関心を向ける人物がいるというのは新鮮な発見だった。
 戸山翻訳農場
戸山翻訳農場



