戸山翻訳農場
作業時間
月曜 14:45~18:00
木曜 16:30~18:00
金曜 18:00〜21:30?
ブログ
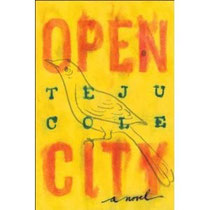
「普段歩いている時や何気なく電車を待っている時って、何を考えている?」
ある時ふと、友人とそんな話になった。そうやって改めて自分を振り返ってみるのも面白い。何気なく、無意識に行動している時にも思考というものは常に働いているのだ。深刻なことから、取るに足らないこと、重要なこと、些末なこと、ふと思うこと、思い出すこと、個人的な出来事、明日のこと、遠い未来のこと、昔のこと、誰かのこと。例えば、こんな風に日常の中でとめどなく流れていく思考を言葉にして、紡いでみるとどうなるだろうか。TEJU COLEの『OPEN CITY』はそんな一冊である。
『OPEN CITY』はナイジェリアとドイツの血を引く精神科医の主人公、ジュリアスがニューヨークの街(途中ベルギーに舞台が変わる場面もあるが)を目的もなく歩き回りながら、自己と向き合う姿を描いたものである。それだけである。簡単に言ってしまえばこの小説は一人の男の内面の記録とも言える。季節の変化から感じること、目にしたもの、聞こえてくるものから思うこと、家族のこと、別れた彼女のこと、親しくしている教授のこと、戦争のこと、民族のこと、政治のこと、生命のこと、トコジラミのこと。日常の中の些末なことや身近な事柄から、「人間とは何か?」という根源的な問いかけまで、彼の思考は現在や過去を絶えず横断し、時に彷徨い、時に行き場を見失う。結局のところ「自分」という存在は、他者との差異や、自分が記憶している“過去”の集積でしか確かめることができず、「今、ここにいる自分」とは、非常に不安定で、曖昧なものである。自分とは何か、他者とは何か―ジュリアスはそんなことを問いかけるように、街を歩く。しかし、どれほど思考を巡らせてみても、それは彼にとって、孤独を確認する作業にしかならない。例え、どれほど多くの他者と共にいたとしても、だ。
大勢の買い物客と労働者の間をかいくぐり、道路工事とタクシーのクラクションから抜け出した。せわしない街を歩き、たくさんの人々、百人以上、千人にさえのぼるかもしれないが、そうした人々を一日のうちに見ることにも慣れたが、こうした無数の顔を見ても孤独な気持ちが和らぐことはなかった。むしろ、孤独は深まった。
ジュリアスは孤独である。父は亡くなり、母との折り合いは悪く、深い愛情を向けてくれていた祖母の行方もわからない。ニューヨークに住む彼に、帰る場所はない。付き合っていた彼女のナデージュは別の男の元に行ってしまい、ほのかな好意を持っていたモジにも突然冷たく背を向けられ、友人もトコジラミが原因でニューヨークを離れてしまう。親しくしていた教授は、がんで亡くなってしまうが、葬儀は身内だけということで、電話口では詳細すら教えてもらえない。ジュリアスの自己は他者との関係性の中にはない。また、ジュリアス自身、非常に内向的な人物で、人に対して心を閉ざし、深い関係になるのをどことなく避けているようなところがある。彼はいつも他者と距離を置き、作品中にも人の言動を疑うような面や、自分をさらけ出すのを避けようとしている場面が見受けられる。
僕は一瞬、彼女が謎解きを大袈裟なものに拡大して、彼女が誰なのか、僕を上手い事丸め込んで、言わせようとしているのではないかと恐れたのだが、彼女は自分で自己紹介をし、僕の記憶は蘇った。(第十二章・モジとの再会の場面)
母と祖母も戦争の終わり頃、そしてその後も難民としてそこにいて、僕自身もある意味ではベルリン人だということは言わなかった。もう少し話を続けていたなら、僕は自分がナイジェリアのラゴス出身だということだけを告げていただろう。(第十二章・写真展で出会った男性と会話した後)
彼は対話においても大抵は聞き手である。また、自分の意見を述べる前から、それが無意味で議論をややこしくしてしまうと決めつけているような節もある。そんな彼が自分をさらけ出せるのは、街を散歩して、自由な思考をめぐらせている時であった。だから彼には散歩が必要だった。彼にとって歩くことは、自分自身を解放することでもあり、不安定な自己を確立させる行為でもあるのだ。
そうしてこの作品には、ジュリアスの目に映る様々な情景が描かれる。しかし細かすぎるまでの描写や、年号をも含むあらゆる分野の知識などが次々と出てくる一方で、作品中には語られていない事実が随分と多い事も指摘しておかなければいけない。果たして、この語り手のジュリアスは信頼できる人物なのだろうか?
「死は完全なる眼である」
人間の目には盲点が存在していて、見ているつもりでも、「見えていない」ものが存在している。生きている限り人は、完全ではいられない。常にどこかで何かが見落とされているのだ。どんなに優れた人であろうが、全てを俯瞰することはできない。『Open City』で描かれ、また描かれなかったものは何か。そういった視点をもってこの作品を見るのも非常に面白い。ジュリアスは明らかに、自分の話に語られていない事実があることを自覚している、確信犯であるからだ。
著者のTEJU COLEはナイジェリア人の両親の元に生まれ、ナイジェリアで育った。その後1992年、十七歳の時にアメリカへと渡る。彼は作家であり、写真家、初期オランダアートの歴史家でもある。本作は著者のデビュー作であり、The Seattle TimesやThe New York Times、The New Yorkerをはじめとして、各紙で非常に高い評価を受けた。また、ペン・フォークナー賞、外国文学賞、ニューヨークシティ・ブックアワードなどを受賞、他にも数々の賞にノミネートされている。
力強く、ドキドキさせる人間の魂についての探求だ。これは全くもって独自の作風で、知的興奮を引き起こし、私達を惹きつけ、魅惑する文体を持っている
—Time Magazine
不朽のデビュー作だ。まさに文学があるべき姿である。作品には思想と信条があり、国境線を曖昧にする。憐み深く、熟練された作品である
―The New York Times
読者はジュリアスの精神性の深さを感じるだけでなく、彼のアイデンティティの脆さも感じるだろう
―Los Angeles Times
立ち止まって日常を観察すると、世界はあらゆるものと繋がっている。ジュリアスにとっては、目に映るあらゆるものは時空を超えて通じ合っている。ありふれた世界も重ね合わせるものによって、姿を変える。『OPEN CITY』を読み終わる頃には、目の前の風景が、少し変わって見えてくるかもしれない。
 戸山翻訳農場
戸山翻訳農場



